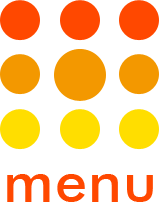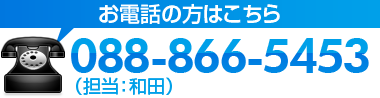ポップコーンの原材料、トウモロコシの歴史から解説します
トウモロコシの原産地はメキシコやグアテマラ等の中南米付近だと言われています。

トウモロコシは1961年にメキシコ南部で八千年前に栽培された痕跡が見つかり、
その後、メキシコから南北アメリカ大陸へ渡り、主要農産物となったと言われています。
その後、15世紀末にアメリカ大陸に到達したコロンブスがスペインへ持ち帰ったことにより、ヨーロッパ諸島、北アフリカ、中近東、1500年代後半にはイギリス、
東ヨーロッパまで広がり、16世紀初めにポルトガルからアジアへと伝わったそうです。
日本に伝来したのは安土桃山時代の1579年で、ポルトガルから長崎、または四国に『フリントコーン(硬粒種)』と言われる品種でした。
フリントコーン(ポップコーンの元)は、加工して食用もしくは家畜用飼料や工業用の
原料に使用される品種で、角状デンプンと呼ばれる硬いデンプンが粒の全体についているのが特徴で、現在でもメキシコ料理のタコス、トルティーヤにこの品種が使われます。
ポップコーンに使われる『爆裂種』は、このフリントコーンから生まれたものなのです。
ポップコーンの原料は爆裂種
1579年に、長崎か四国に爆裂種のルーツ、フリントコーンが伝来したと言われています。
…四国の海の玄関といえば高知…もしかして日本で最初にポップコーンを食べたのは高知県民!?
と高知県民の私は妄想が膨らみます。
当時、南蛮船が運んで来たことから「ナンバンキビ(玉蜀黍、南蛮黍)」と呼ばれ、九州や四国の山間部で栽培が定着してからは、中国、近畿、東海地方と北上し、関東周辺の山地へ伝わったとされています。その後、江戸時代に入ってからは、特に水田や畑地が少ない地域で、重要な食糧となっていきます。
本格的に栽培されるようになったのは、明治時代に入ってからで、北海道開拓に伴い、北海道農事試験場がスイートコーン(甘味種)である『ゴールデンバンタム』という品種をアメリカから導入したことが始まりです。 第二次大戦後には、北海道から南下して本州に広まり、日本全土でのとうもろこし栽培が始まりました。
ポルトガル船より伝わったポップコーン
ポルトガル船が日本に爆裂種の元になった品種『フリントコーン』を持ち込み、四国ではどうやら昔から、トウモロコシを加熱して爆裂させたやつを食べていたそうなんです。
大正時代から昭和初期の食生活の記録を、都道府県ごとにまとめた農文協の「聞き書」シリーズを見ると、当時の四国では『焼いてはじかせた、真っ白い花のように開いたきれいで香ばしい』トウモロコシをおやつ等にしていたという記述があります。
『はぜとうきび』、愛媛、高知では『花きび』。海を渡って四国の対岸にあたる和歌山では『花』と呼ばれて親しまれていたそうです。当時の文献を辿ると『他の地域でも江戸期から明治にかけて四国で育まれた和製ポップコーンが和歌山へと伝わったと考えるのが自然な道筋だ』と記載されていて、やはり縁を感じずにはいられない私なのでした。
高知を代表するポップコーンブランド「マックのポップコーン」
昭和34年ころ、高知市秦で生まれたマックのポップコーン。映画館で販売していたころ「甘くないから美味しくない!」と言われ、砂糖で味付けしたシュガー味が誕生しました。高知県西部では、お醤油やケーキ、パンなど、甘い味付けの食べ物が人気です。
パンの上に羊羹が乗ったパンも有名で、皿鉢料理(さわち料理)にもお寿司と一緒に羊羹が添えられています。お酒は辛口ですが、甘いものをつまみながら飲む方が多いため、塩味のポップコーンよりも、砂糖味のシュガーコーンが一般的。

「県外に出て、映画館でポップコーンを食べてしょっぱくてビックリした!」と話す昭和30〜40年代の地元の方は大変多いです。
また、弊社の商品、シュガーコーンに色を付けた「花きび」は、マックポップコーンを最初に製造していた久保田商会の久保田会長がヒントを得て誕生しました。
会長(当時80歳ほど)に以前伺ったところ、会長が小学生くらいの頃、お百姓さんが「花きびいらんかえ〜」と売り歩いていたそうです。
それをヒントに、昭和40年頃、シュガーコーンに色を付け本当に花のような形の可愛らしい、文字通りの「花」きびが誕生し、それ以降「花きび」はずっと高知で愛され続けています。